Coming Mars 2001 (03)
2001年の火星 (3)
2001年と1954年、1969年、1986年の火星
南 政 次・西田昭徳
★周知の様に十五年乃至十七年毎に似たような火星がやってくる。2001年の火星に似た火星は、前回は1986年、その前は1969年、更にその前は1954年であった。似ていると言っても、必ずしも同じではない。衝の位置をプロットすると、お互いに近いものの、1986年の位置が最も火星の近日点に近く、次は1954年、更にその次は2001年、近日点から最も遠いのは1969年であった。
φ: 中央緯度 δ: 視直径
| Mars in 1954, 1969, 1986 and 2001 |
|---|
| | Opposition | Closest approach | Period where diameter is larger than 10" |
|---|
| 1954 |
24 June
184゚Ls,φ=1゚N |
02 June
189゚Ls, φ=2゚N,δ=21.9" |
05 Apr (141゚Ls)〜24 Oct (259゚Ls) |
|---|
| 1969 |
31 May
164゚Ls,φ=7゚N |
09 June
170゚Ls,φ=9゚N δ=19.5" |
21 Mar (129゚Ls)〜23 Sept (233゚Ls) |
|---|
| 1986 |
10 July
203゚Ls,φ=6゚S |
16 July
206゚Ls,φ=5゚S;δ=23.2" |
10 Apr (151゚Ls)〜07 Nov (278゚Ls) |
|---|
| 2001 |
13 June
177゚Ls,φ=3゚N |
21 June
182゚Ls,φ=4゚N;δ=20.8" |
28 Mar (137゚Ls)〜10 Oct (250゚Ls) |
|---|
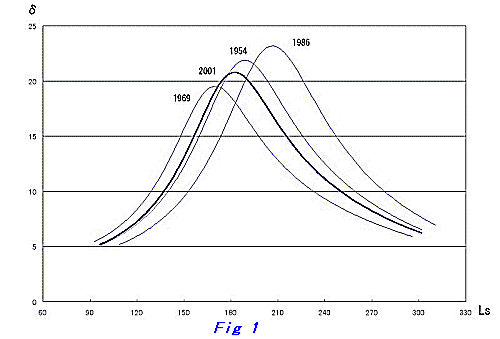 ★火星の離心率は大きいから、これは対衝のときの視直径が、大きい方から1986年、1954年、2001年、1969年と並ぶことを意味している。具体的に視直径δの変化を図示したものが Fig 1 である。1986年の最大視直径が23.2秒角であったのに対し、1969年は19.5秒角であった。図から判るようにそれぞれのカヴァーする季節も幾らか違っている。1969年の最接近の時の季節が170゚Lsであったのに対し、1986年は206゚Lsであったから、かなりの(35度の)差があり、逆に言えば、四回の観測を重ねれば、同一視直径での観測幅が拡がるわけである。実際に、15秒角での範囲は、148゚Ls (28 Apr 1969)から247゚Ls (20 Sept 1986)迄となり、100度幅となる。もちろん、重なる部分も多く、例えば180゚Lsはδ=15"以上で、どの接近でも観測可能であったわけで、これはこのシリーズの特長でもある。
★火星の離心率は大きいから、これは対衝のときの視直径が、大きい方から1986年、1954年、2001年、1969年と並ぶことを意味している。具体的に視直径δの変化を図示したものが Fig 1 である。1986年の最大視直径が23.2秒角であったのに対し、1969年は19.5秒角であった。図から判るようにそれぞれのカヴァーする季節も幾らか違っている。1969年の最接近の時の季節が170゚Lsであったのに対し、1986年は206゚Lsであったから、かなりの(35度の)差があり、逆に言えば、四回の観測を重ねれば、同一視直径での観測幅が拡がるわけである。実際に、15秒角での範囲は、148゚Ls (28 Apr 1969)から247゚Ls (20 Sept 1986)迄となり、100度幅となる。もちろん、重なる部分も多く、例えば180゚Lsはδ=15"以上で、どの接近でも観測可能であったわけで、これはこのシリーズの特長でもある。
★ただ、同じLsが観測可能でも、お互いに同じではない。まず、特定の地方(例えば日本)から眺められる火星面は(同じLsでも)同じではないし、中央緯度φが違っている。
 ★Fig 2 はそのφの違いを示したものである(中心の拡大図は既に#233 p2778に引用してある)。130゚Ls以前、250゚Ls以後はφの変化は似ているのであるが、南半球の春分180゚Ls前後では大きく違っている。矢張り火星の近日点からの距離によって違って、1986年には大きく南半球がこちらに傾いたのに対し、1969年には北半球本意である。2001年は1954年に似て中間型だが、より1969年に近い。1969年には、南極冠と南極雲の区別がかなり困難であった、というより極冠らしい極冠は見られなかったという記憶が筆者の一人(Mn)にはある。1969年には180゚Ls (27 June 1969)の時点でφ=11.4゚Nであった。実際にはMnは梅雨の間、殆ど欠測であったが、七月半ば190゚Lsに至っても燦然とした大型の南極冠は見えていない。一方、1986年には180゚Ls はφ=10.5゚Sであった(1 June 1986)から開きは大きく、このシーズンは南極冠がよく観察可能であった。
★Fig 2 はそのφの違いを示したものである(中心の拡大図は既に#233 p2778に引用してある)。130゚Ls以前、250゚Ls以後はφの変化は似ているのであるが、南半球の春分180゚Ls前後では大きく違っている。矢張り火星の近日点からの距離によって違って、1986年には大きく南半球がこちらに傾いたのに対し、1969年には北半球本意である。2001年は1954年に似て中間型だが、より1969年に近い。1969年には、南極冠と南極雲の区別がかなり困難であった、というより極冠らしい極冠は見られなかったという記憶が筆者の一人(Mn)にはある。1969年には180゚Ls (27 June 1969)の時点でφ=11.4゚Nであった。実際にはMnは梅雨の間、殆ど欠測であったが、七月半ば190゚Lsに至っても燦然とした大型の南極冠は見えていない。一方、1986年には180゚Ls はφ=10.5゚Sであった(1 June 1986)から開きは大きく、このシーズンは南極冠がよく観察可能であった。
★例えば、Mnの観測によれば、既に24 May 1986 (176゚Ls)にはφ=11゚Sで、南極冠内に輝点や蔭を見ている(ω=097゚W)。横浜で述べたように、1999年のMGSが同じ時期の南極冠を写しているし、1977年のVO2の結果も知られている(#231p2736参照)。1986年にはその後南極冠の中央の溶解が速くなり、南極冠は南端で凹みを見せる様になったことは記憶されている方もいよう。1969年にはφの傾きの所爲で、同じ結果は望むべくもなかった。
★2001年接近は、やはり少し困難が伴うが、同じ時期の南極冠の観察は1969年に比べれば遙かに好機である。180゚Lsではφは北を向いているが、さほどではなく140゚Lsから170゚Lsまでは南であるから、南極雲の最後の段階を好く観測できる。しかも、1986年には176゚Lsの時点でδ=18.9"であったが、2001年にはδ=20.4"となっているから、視直径には遜色はない。
★春分直前の南極雲→南極冠の過程で観察の目安に選ばれるべきはヘッラスである。横浜で例示したように、海老沢嗣郎氏は1986年の場合、136゚Ls、165゚Ls、187゚Lsのヘッラスを含む同じ地方時が選ばれ、比較されている。海老沢氏の場合、フランスでの観測が入るようだが、定点では同じωは約四十日、Lsで約二十度跳ぶことになる。しかし、これで、南極と共にヘッラスが靄っている状態、ヘッラスが晴れているが、南極が未だフッドに覆われている状態、両方とも晴れてきた場合、等が分別できる。
★2001年の場合、日本からは3 Mar 2001 (124゚Ls)の18:00GMT前後、10 Apr 2001 (143゚Ls) 18:00GMTあたりでのヘッラスの観測が最初のキーポイントになる。Smith-Smithの古典的な結果ではヘッラス靄は150゚Lsで崩壊し始め、170゚Lsでは消失する。260゚Lsあたりでは小さな瘤が出ることがある。しかし、これは平均値であって、毎回精査する必要がある。
★横浜で発表された中島守正(Nk)氏の表では、1973年には200゚Lsから220゚Lsあたりまでヘッラスは靄っていたという記録がある他、1971年には250゚Lsにヘッラス北部に白雲が見られている等、これらは2003、2005年に相当する結果だが、2001年にも守備範囲に入る。
★1986年の結果では187゚Lsには既に南極冠は溶け始めているから、ヘッラスの後は、春分前後は南極冠を心して観察しなければならない。
★Fig 2から判るように、1956年型の黄雲の発生時期245゚Ls (2001年には十月初め)には既にφは南を向いているから、観測には視直径と低空による悪シーイング以外困難はない。最近はグローバルなものは見られないが、1997年にはMGSがノアキスにかなり大きな黄塵を見付け、それが224゚Ls (26 Nov 1997)からであったから、2001年なら八月末からということになる。この黄塵については
http://www.msss.com/mars_images/moc/science_paper/f7c/index.html
を参照されたい。
★1954年以前の似たような接近年を更に挙げれば、1937年、1922年、1907年、1890年、1875年等となる。しかし、この限りでは、1986年の南半球型を越えるものはない。1907年は1986年にかなり近い(79年周期である)。一方、1937年は1969年よりも北半球型で、最大視直径は18.4秒角にしかならなかった(佐伯恆夫氏が花山天文台で観測された年で、2 June 1937に好シーイングに恵まれている。最接近は28 Mayであった)。なお、このシリーズの内では1937年は、南中時の高度が最も高かった(視赤緯は-20゚40'であった)。一方、1986年を凌ぐ南半球型は79年後の2065年に訪れる。
訂 正: #236 p2819 の Coming (1)の二番目のパラグラフに「年末には−5゜まで落ちる」というのは間違いで、年末には−12゜近くになります。−5゜は十二月の初めデータでした。
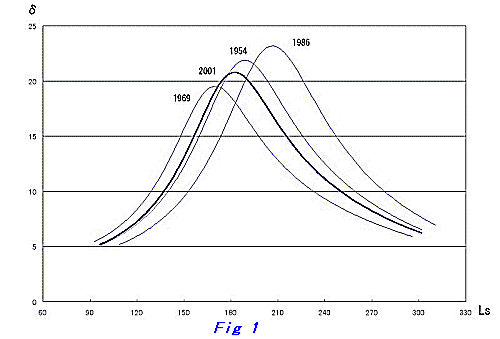 ★火星の離心率は大きいから、これは対衝のときの視直径が、大きい方から1986年、1954年、2001年、1969年と並ぶことを意味している。具体的に視直径δの変化を図示したものが Fig 1 である。1986年の最大視直径が23.2秒角であったのに対し、1969年は19.5秒角であった。図から判るようにそれぞれのカヴァーする季節も幾らか違っている。1969年の最接近の時の季節が170゚Lsであったのに対し、1986年は206゚Lsであったから、かなりの(35度の)差があり、逆に言えば、四回の観測を重ねれば、同一視直径での観測幅が拡がるわけである。実際に、15秒角での範囲は、148゚Ls (28 Apr 1969)から247゚Ls (20 Sept 1986)迄となり、100度幅となる。もちろん、重なる部分も多く、例えば180゚Lsはδ=15"以上で、どの接近でも観測可能であったわけで、これはこのシリーズの特長でもある。
★火星の離心率は大きいから、これは対衝のときの視直径が、大きい方から1986年、1954年、2001年、1969年と並ぶことを意味している。具体的に視直径δの変化を図示したものが Fig 1 である。1986年の最大視直径が23.2秒角であったのに対し、1969年は19.5秒角であった。図から判るようにそれぞれのカヴァーする季節も幾らか違っている。1969年の最接近の時の季節が170゚Lsであったのに対し、1986年は206゚Lsであったから、かなりの(35度の)差があり、逆に言えば、四回の観測を重ねれば、同一視直径での観測幅が拡がるわけである。実際に、15秒角での範囲は、148゚Ls (28 Apr 1969)から247゚Ls (20 Sept 1986)迄となり、100度幅となる。もちろん、重なる部分も多く、例えば180゚Lsはδ=15"以上で、どの接近でも観測可能であったわけで、これはこのシリーズの特長でもある。 ★Fig 2 はそのφの違いを示したものである(中心の拡大図は既に#233 p2778に引用してある)。130゚Ls以前、250゚Ls以後はφの変化は似ているのであるが、南半球の春分180゚Ls前後では大きく違っている。矢張り火星の近日点からの距離によって違って、1986年には大きく南半球がこちらに傾いたのに対し、1969年には北半球本意である。2001年は1954年に似て中間型だが、より1969年に近い。1969年には、南極冠と南極雲の区別がかなり困難であった、というより極冠らしい極冠は見られなかったという記憶が筆者の一人(Mn)にはある。1969年には180゚Ls (27 June 1969)の時点でφ=11.4゚Nであった。実際にはMnは梅雨の間、殆ど欠測であったが、七月半ば190゚Lsに至っても燦然とした大型の南極冠は見えていない。一方、1986年には180゚Ls はφ=10.5゚Sであった(1 June 1986)から開きは大きく、このシーズンは南極冠がよく観察可能であった。
★Fig 2 はそのφの違いを示したものである(中心の拡大図は既に#233 p2778に引用してある)。130゚Ls以前、250゚Ls以後はφの変化は似ているのであるが、南半球の春分180゚Ls前後では大きく違っている。矢張り火星の近日点からの距離によって違って、1986年には大きく南半球がこちらに傾いたのに対し、1969年には北半球本意である。2001年は1954年に似て中間型だが、より1969年に近い。1969年には、南極冠と南極雲の区別がかなり困難であった、というより極冠らしい極冠は見られなかったという記憶が筆者の一人(Mn)にはある。1969年には180゚Ls (27 June 1969)の時点でφ=11.4゚Nであった。実際にはMnは梅雨の間、殆ど欠測であったが、七月半ば190゚Lsに至っても燦然とした大型の南極冠は見えていない。一方、1986年には180゚Ls はφ=10.5゚Sであった(1 June 1986)から開きは大きく、このシーズンは南極冠がよく観察可能であった。