矢印の先にある動かない光点が 3I/ATLAS
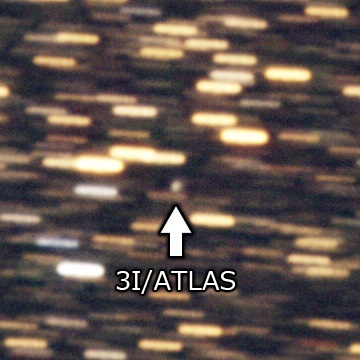
3I/ATLAS を追尾しているため、背景の星は移動して線になっている
太陽系には惑星以外にも小惑星や彗星といった小天体がたくさん存在します。 それらに混じって観測史上3例目となる太陽系外から飛来した天体 3I/ATLAS が7月1日に発見されました。 太陽系の外、つまり恒星間空間の天体という意味で Interstellar の頭文字と3番目の数字を組み合わせた符号に続き、 発見者 (発見機関) であるATLASプロジェクト (小惑星地球衝突最終警報システム : Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) の名前がついています※。
冒頭の動画は2025年7月15日にせいめい望遠鏡を用いて撮影した動画で、中央付近に 3I/ATLAS が写っています。 高速で運動しているこの天体を追尾しているため、周囲の恒星が移動しているように見えます。 図1の小さな動画は中央付近を切り出して拡大したもの、図2は動画の各コマを足し合わせて淡い部分まで見えるようにした画像です。
※この天体は、発見直後は仮名称 A11pl3Z と呼ばれていました。その後、過去の観測データや新たな観測データから彗星活動が報告され、C/2025 N1 (ATLAS) という彗星としての名称も付けられています。
恒星間天体
近年、太陽系外にもたくさんの惑星系が発見されていますが、極めて遠方で詳細な観測が難しいことから、その成り立ちについては多くの不定性が残されています。 太陽系外から飛来した天体を観測し、その軌道や物理的性質を太陽系内の天体と比較すれば、惑星形成モデルが太陽系以外の恒星系にも当てはまるのかどうかを検証することができます。
しかし、これまでに報告された恒星間天体は 1I/'Oumuamua (2017年)、2I/Borisov (2019年) のわずか2例にとどまり、恒星間天体に関する知見は非常に限られていました。 そのような中、3I/ATLAS は、発見直後に太陽系外由来であることを示す軌道が判明し、世界中の望遠鏡による迅速な追跡観測が行われました。 3I/ATLASは、2I/Borisovと同様に彗星活動を示す様子が複数の観測者により報告され、太陽系外から飛来した彗星型の恒星間天体であることが明らかになりました。
すでに、波長ごとの光の強度(スペクトル)を調べることで3I/ATLASの表面物質の性質が推定され複数の論文が発表されていますが、研究グループごとに異なる結果が得られており、独立した観測データの取得が求められています。 私たちは、せいめい望遠鏡の大口径と多色同時撮像という特長を活かし、迅速な追観測を実施しました。 取得したデータを詳細に解析することで、史上3例目となる恒星間天体 3I/ATLAS の物理的性質の解明に貢献します。
執筆協力:紅山 仁 (コートダジュール天文台 / 東京大学)
地球に接近する小型の小惑星を中心に観測し、その性質について調べている。
※このページに掲載している動画・画像は、せいめい望遠鏡で紅山さんが観測したデータをご提供いただき作成しました。
掩蔽観測への挑戦
3I/ATLASは、2025年7月現在へびつかい座といて座の境界付近に見えています。このあたりは銀河系の中心方向にあたるため、背景に大量の星が写っています。 このような条件では恒星の前を天体が通過して一時的に光が遮られる現象である掩蔽(えんぺい)を捉えるチャンスが通常よりも多くなります。 掩蔽観測では、恒星が暗くなるタイミングや継続時間を測定することで、巨大な望遠鏡を使っても点にしか見えない小天体であっても、大きさや形状を高精度に知ることができます。 加えて、光が遮られる前後の暗くなり方を詳しく測定することで、小天体の周囲にある大気やダスト等の存在を調べることができる強力な手法です。
これまでに恒星間天体による掩蔽現象の観測例は存在していません。 観測に成功すれば、3I/ATLASの物理的性質に迫る貴重な情報が得られると期待されます。 現在、せいめい望遠鏡の極めて高い集光力とユニークな動画観測性能を活かし、世界初となる掩蔽現象の検出に挑戦しています。
執筆協力:有松 亘 (京都大学)
太陽系外縁天体による掩蔽観測や、小天体が惑星に突入する際の発光現象を観測している。
トップ動画
2025年7月15日22時05分(JST)
観測装置:TriCCS
露光時間:g, r, i各バンド 60秒×10フレームを秒間2フレームで再生(120倍速)
写野:12.3x6.9arcmin
Ⓒ 京都大学岡山天文台/ 東京大学